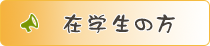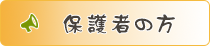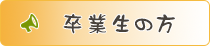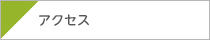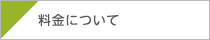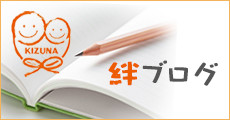HOME > 鈴木 俊一
鈴木 俊一
目に見えないモノ=人と人のつながり=「絆」
 学生時代より、進学塾や家庭教師をしてきました。 公立中学校や私立高校にて教壇にも立ってきました。 野球部の顧問や特別支援学級の担任などにも携わらせていただきました。 旧内原町就学指導委員や家庭支援専門相談員として様々な子どもたちや保護者の対応にもあたりました。
学生時代より、進学塾や家庭教師をしてきました。 公立中学校や私立高校にて教壇にも立ってきました。 野球部の顧問や特別支援学級の担任などにも携わらせていただきました。 旧内原町就学指導委員や家庭支援専門相談員として様々な子どもたちや保護者の対応にもあたりました。数千人の子どもたちやその保護者との関わりの中で、子どもたちの学力向上に必要不可欠なものの一つとして、重要だと実感したのが「絆」でした。
東日本大震災以後、その「絆」が注目されるようになりました。
日本は、高度経済成長期からバブル経済崩壊を経て、物質的なモノの豊かさに、人間の価値を見出す傾向が強くなってきたと捉えています。その価値観が、大きく転換した起点があの震災であったと思います。 どんなに貨幣を所有していたとしても、モノが存在しなければ、購入することができないことを思い知らされました。 スーパーやコンビニエンスストアの棚に商品がほとんどなくなってしまったことが、その証拠であります。 その際、地域の方々との助けあい、支えあい、ふれあいを少なからず意識したのではないでしょうか。
 モノよりも「絆」が大切かもしれないとふと感じるときが誰しもあったと思います。 目に見えるモノよりも、目に見えない「絆」が、いかに我々の人生に大きな影響を与えているかと考えたのであります。 言い換えれば、文科省の新学習指導要領に云う「生きる力」が、目に見えるモノを安く大量に提供することに徹してきた時代から脱却し、 目に見えないモノ=人と人のつながり=「絆」に価値を転換することにあたります。
モノよりも「絆」が大切かもしれないとふと感じるときが誰しもあったと思います。 目に見えるモノよりも、目に見えない「絆」が、いかに我々の人生に大きな影響を与えているかと考えたのであります。 言い換えれば、文科省の新学習指導要領に云う「生きる力」が、目に見えるモノを安く大量に提供することに徹してきた時代から脱却し、 目に見えないモノ=人と人のつながり=「絆」に価値を転換することにあたります。過去には、子どもたちの成長に関わる大人は、両親はもちろんのこと、祖父母などの親戚、学校の先生方、 そして、地域の方々がおりました。ところが、昨今、近所のうるさいおじさん的な存在が少なくなってきたと聞いております。
子どもの発達の場は、家庭、学校、地域であります。
それぞれ役割があり、そのバランスが保たれて、子どもはより良い発達をしていくのです。 近所のうるさいおじさんがいなくなってきたということは、このバランスが崩れてきたことを意味しています。 そして、バランスが崩れてきたということは、子どもたちのより良い発達が阻害されているということになります。
そこで、私は、一塾講師として塾生の学力向上に全力を注ぐのはもちろんのこと、 子どもの成長を励まし、見守る地域の顔として貢献してまいりたいと決意いたしました。
私のもとから巣立っていった生徒たちが、中学卒業後も立ち寄って元気な笑顔とその成長ぶりを垣間見せてくれていることは、感謝しています。 次世代を担う子どもたちの支えとなってまいります。それが、「絆」の使命であると確信しています。
 これからの時代は、物質的な豊かさから心の豊かさへとその価値観が移行する過渡期であると捉えています。 高校を卒業しても、大学を卒業しても、確実に就職できるという時代ではなくなってきています。 社会が大きく変化している中では、教育というものも変化せざるをえません。
これからの時代は、物質的な豊かさから心の豊かさへとその価値観が移行する過渡期であると捉えています。 高校を卒業しても、大学を卒業しても、確実に就職できるという時代ではなくなってきています。 社会が大きく変化している中では、教育というものも変化せざるをえません。確かに、これまでの詰め込み型の勉強も否定できません。 しかし、それだけでは、「生きる力」を育むことは不可能です。 大学や予備校は講義といいます。高校や中学では授業といいます。 前者は講師の一方通行なので、生徒が分かると分からずとに関わらず、進んでしまいます。 授業は相互通行でなければなりません。 お互いの表情やしぐさ、声の強弱などでも意思疎通を図りながら進んでいく授業を展開していくのが「絆」であります。
そういう一人ひとりとの関わりあいの結びつきの強さを「絆」と私は考えております。
きれいな建物でも、有名な名前があっても、実際に、子どもたちと関わる先生がどんな先生なのかが重要であるのではないでしょうか。 年度の途中で先生が変わるようなことはありません。 何より、先生と生徒のしっかりとした「絆」があってこそ、学力向上、そして、「生きる力」を育むことができるとの方針が打ち立てられたからです。
ここでいう「生きる力」とは、「絆」だけではありません。
集中力、思考力、直観力、想像力、問題解決能力などの強化も必要であります。 年少時からの成功体験の積み重ねも重要です。生徒の脳を活性化するのにぴったりしたのが、Kids Now Puzzleというまったく新しい学習システムでした。
 これまでの詰め込み型の学習では、自転車のペダルを片足でこいでいるようなものではなかったかとみえました。そこで、Kids Now Puzzleを一緒に取り組むことにより、両足で人生の王道をこいでいくことができるようになりました。 単に覚えることだけでなく、子どもたちの考える力を伸ばしていきたいのです。
これまでの詰め込み型の学習では、自転車のペダルを片足でこいでいるようなものではなかったかとみえました。そこで、Kids Now Puzzleを一緒に取り組むことにより、両足で人生の王道をこいでいくことができるようになりました。 単に覚えることだけでなく、子どもたちの考える力を伸ばしていきたいのです。Kids Now Puzzleは、「ひらめき」を育てる学習でもあります。脳内のメカニズムを連続して活性化して、創造性による知識社会への適応を重要視する教育に取り組んでまいります。
塾を開講するにあたり、塾生の保護者からお電話をいただきました。
「先生との『絆』が大切ですから・・・」
その時、私が歩んできたものが一点に凝縮された思いがしました。
そして、こちらから提供するだけでなく、保護者や生徒の声に耳を傾ける塾があってもいいのではないか。 生徒と保護者と講師が互いに意見を出し合ってつくり上げる塾があってもいいのではないかと思いました。
開塾した当初は、塾名がありませんでした。
ある保護者からの電話をきっかけとして、これまで述べた私の半生を振り返ってみて、「絆」と命名したのであります。
これからは、地域の「絆」となれますよう精進してまいる所存であります。
21世紀は、誰もが幸せを実感できる時代へとすべく、教育活動を通じて地域社会に奉仕してまいります。新しい時代は、もうそこまで来ています。
地域に喜ばれる存在となるべく、地元の総合教育機関の一端として、次世代の育成に尽力してまいります。